その前夜 2
その前夜 二
文化と帝国主義
エドワード・サイードの『文化と帝国主義2』をやっと読むことができた。
なまけていたんではない。二分冊の翻訳の2がなかなか刊行されなかったせいである。よって、1の内容を忘れかけたころに2を読むことになった。2を通読し、1を引っ張り出してきて序言を読み直す。素朴な感想をいえば、後半になって書物としての完成度が薄まっていると感じた。それは後半の叙述が、前半の文学研究という領域から脱し、現代世界の特殊な後期帝国主義段階に直接結び合っているからだ。湾岸戦争への言及が後半の多くを占めるように、現代世界とは、湾岸戦争直後の九〇年代社会を指している。(湾岸戦争論にはべつに独創的なところはない。それもまた――時間が経ってしまったから余分にそう感じるのか?――この書物が部分的にしろ時事論に流されていると感じさせる要因だろう)。アメリカ帝国の派遣的な一国帝国主義が不均衡に君臨している世界だ。いくらか雑駁に読めるという結果は、かえってサイードの文化論者としての誠実さを示しているのかもしれない。
著者は、世界を解釈するのではなく、相変わらず、変革のヴィジョンを手探りすることを自分に課しているのだ。
にもかかわらず、安逸な処方箋を書くことができないという意味では、『文化と帝国主義』全体の結語は曖昧なものだ。他ならぬこの曖昧さがサイードへの信頼を新たにさせるとしても、書物そのものは断固たる言い切りによって、堂々の幕を閉じる体裁ではない。
社会主義の理想が崩壊したあと、今世紀の思潮を一貫して支えてきたアメリカ的新秩序が全世界にネットワークを張りめぐらせるに到った「現在」。われわれの混迷は、サイードも絶えず強調しているように、どの社会であれ国家であれ民族であれ、共通の彩りを帯びているようだ。まわりを見回して、われわれの混迷はわれわれのみの混迷ではないと気づくのは、たしかに、いくらか心強い体験だ。「われわれ」とここで指示しているのは、われわれ日本人社会のことだ。
誤解なきように断っておくが、『文化と帝国主義2』の記述全体がおしなべて統一されていない文章の寄せ集めという印象を与えるわけではない。1所収の第二章「強化されたヴィジョン」が、コンラッド、オースティン、ヴェルディ、キプリング、カミュを端正に論じられているように、2所収の第三章「抵抗と対立」においては、フランツ・ファノン、C・L・R・ジェイムズ、エメ・セゼール、ジョージ・アントニウス(この人の名は知らなかった)が、敬意をもって評価される。それにとどまらず、帝国主義本国に属する詩人イェイツの像が、より「植民地」アイルランドに近く、脱構築〈デコンストラクション〉される。
だから『文化と帝国主義』を精密に読んでいくなら、文学研究の枠からはみ出る「開かれた記述」は、1の第一章と2の第四章とに分散していることがわかる。それがサイードの構成法なのであり、彼は統一された静的な文学研究などに自分の叙述を領域化することを潔しと思わなかったのだろう。――この一文は、二分冊をかなりの中断をはさんでざっと通読しただけの用意で書いているので、いささか不正確のところもあるかと思う。まあ、感想を優先して進めたい。
ファノン、ジェイムズ、セゼール、アントニウス。いずれも植民地出身の有色人種の歴史家への記述は、さまざまな陰影はあるにしても、感情的な親近は明らかだ。とくにファノンを引用するさいの熱狂。そしてジェイムズとの会見を報告するさりげない一行の燃え立つような興奮。
それらを、第二章の分析対象とされたヨーロッパの宗主国文学者の研究と同列に置くことは、正確とはいいがたいだろう。
いってみれば、そうした印象が、余分に第四章「支配から自由な未来」の散漫さを、それが書物全体の結語にあたるにもかかわらず、増大させるのかもしれない。
第三章末尾に近く、ジェイムズの歴史書とセゼールの詩を衝突させたあと、自然と流れ出してくる次の数行こそ、この本の祈りのような結語に当たると思われてならない。
「詩人のヴィジョンは、経済でもなければ政治でもない。それは他に類のないものであり、それ自身で真実であるから、他の真実を必要としない。だがそこに詩的受肉〈ポエティック・インカーネイション〉を見落とすなら、それは俗悪な人種差別におちいるだろう」
しかしながら、それを指摘するのみでは、いくら素朴な感想文でも不充分のそしりを免れまい。サイードがあえて第四章を書き加えねばならなかったことも了解がつく。《ナイーヴなユートピア志向に陥ることなく、かといって絶望的なペシミズムに陥ることもなく……》といった原理論で閉じることが可能ならば、そもそも「文化と帝国主義」といったテーマで書物が書かれる必要などないではないか。これは著者の基本的なスタンスを示す、最も手厳しい循環的な難問〈アポリア〉だ。第四章は、痛みに満ちた現認報告とでもいうしかない内容だ。それ以外の文体は採りようもなかった。そして書物に必要な結語は、その報告からは弾き飛ばされている。
サイードは現存する文芸批評家として、(おそらくジョージ・スタイナーと並ぶ)知性と広い視野とそして(これが肝要のことだが)未来への不動のしかし痛みにみちたオプティミズムを兼ね備えた、類いまれな知識人である。そうした存在として、当然のことに、文学研究者プロパーの仕事を嫌ってきた。第四章が明敏に認めていることは、かつては成立していたグローバルな文化概念がばらばらに解体されてしまっている現状だ。結果的に有力になっているのは、狭い特定のジャンルで卓越するテクノクラートだ。
彼ら専門技術者たちは《原則としてローカルな問題解決の能力に長けているぶん、解放や啓蒙という大きな物語〈グランド・ナラティヴ〉によって設定された大きな問題に取り組むことはできないのだが、そのくせ、慎重に審査された資格をもった政策専門家として居すわり、国際情勢を方向付ける安全保障管理者たちに奉仕するのである。》
これは文化的にみれば、ポストモダン以降の「全世界的な」傾向といえよう。そしてこうした事態は、政治的にいって馬鹿げた強権による専制の温床でもあるだろう。むしろ民主主義国家の民衆ほど積極的に柔らかいファシズムを待望するのかもしれない。戦後日本をユートピアと呼ぶつもりはないが、少なくとも一国的エゴイズムの安全と平和と繁栄(十年ほど前までは)などは保証されてきた。その「楽園」は今やさまざまな階層から非難を受けて、凋落の道を転がり堕ちている。
サイードの書物では、コンラッドが全編を縦断するトリックスターのようにふるまっている。『闇の奥』と『ノストローモ』は、書かれてから百年を過ぎても依然としてその重要度を喪っていない。基本的には帝国主義の宣伝文書でありながら、一方では、反帝国主義の痛烈なテキストでもありえている。コンラッドを例にとるなら、帝国主義と反帝国主義とが両義的に入り組んで一人の表現者を縛呪することに、何ら矛盾は見い出せないのだ。
サイードは日本についてふれて、日本が「厄介な例を示すように」と不用意に書いているように、日本という事例に関してはあまり多大な関心を寄せていない。三等級の帝国主義国家だったので、ポストコロニアル研究の重大なテーマに寄与しないのかもしれない。サイードの視線は、オリエンタリズムを特化するヨーロッパ‐アメリカ的普遍には批判的に向くが、そのフレームのなかに日本は入ってこないかのようだ。このことは、サイードの著作のほとんどが翻訳されている国での奇妙なパラドックスだ。
局地日本においても、ポストコロニアニズムの観点から文学史を再編的に読み直す仕事は必要とされるはずだ。
あるいは、もう手遅れということだろうか。
2001.8.27
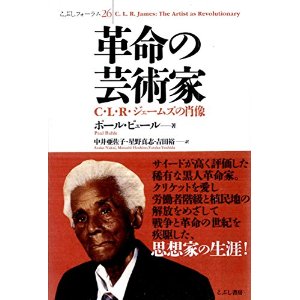
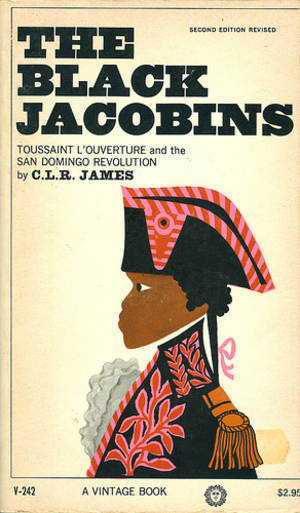
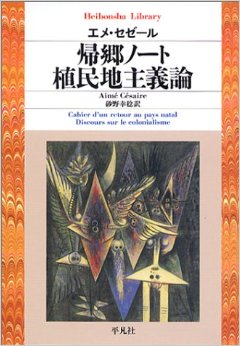
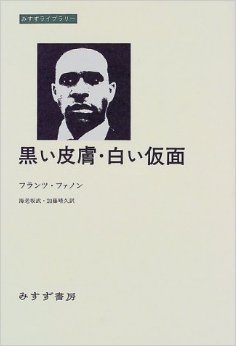
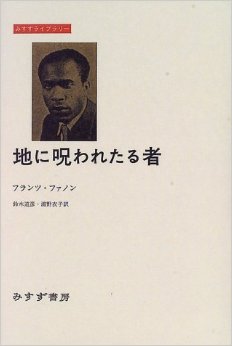
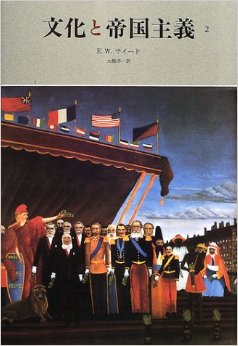
Share this content:
コメントを送信