更新日記2003.11.01
必要があって火野葦平の『陸軍』を読み出した。初刊が昭和二十年八月十五日の奥付を持つことで有名であり、市販されることなく焼かれたとする「伝説」(そう明記してある年譜もあるが、じっさいはけっこう出回っていたらしい)すら伝えられる作品。
今なお読むにたえる水準と密度を備えていることに驚いた。大新聞に一年間連載されたものとはいえ、その時期が時期だから、資料として目を通しておけばいいというくらいの気持ちで向かったのだが、その大衆小説としての堅固さに舌を巻いたのだ。
けれど感嘆したのは、戦後なんども新装版を重ねている火野作品の庶民性のしたたかさについてでは、むしろない。火野が確実に所属していると思われる日本人性が、まったく今日も変わらず脈々とこの社会の底に流れていることが衝撃だったのだ。
『陸軍』は、近代化以来七十年ひた走りに走りつづけた日本の軍国主義が(好戦的とはほど遠い)常民によって支えられていることを、最初の一行から、一字 一句、行間のすべてを動員して語ってくる。この作品が書かれてから六十年近くが経過しているが、その生命は消えていないのである。
のみならず、恐れ入ることに、『陸軍』は今日よみがえってくるにふさわしい、いや、今日あらためて発見されるにふさわしい精神を帯びた作品なのだ――と か、したり顔でいうやつが『諸君』とか『正論』あたりに登場してきそうな気がする。火野の描いた日本人の兵隊たちの顔がなんと昨今の日本人そのままなの で、恐怖すらおぼえた。まことに戦後の平和憲法の時代は消尽しつくされ、ひとめぐり巡って、また野蛮な世の中がやってくる。宿命のごとく。
警告も反省も誓言もおしなべて虚妄でしかなかったのか?
いっしょに読んだ山岡荘八や丹羽文雄のものはべつに感心しなかった。絶叫や説教――要するに時代色が鼻につくのだ。もちろ ん『陸軍』にだって、主要人物の一人が瀕死の身体を起こして、最後の力をふりしぼり皇居の方角を向き、軍人勅語を唱えてから事切れるといった、薄っぺらい 作り物の迎合的シーンは出てくる。それもクライマックスあたりに。ただ戦争という「異常な日常」への迫り方が群を抜いているので、時局性の濃い部分を差し 引いても作品性の生命は残るのだ。
気になるのは、こうした受容が以前のわたしには決して訪れなかったろうという点だ。年を取ったからではなく、戦争への対し方が変わったせいだろう。転向したからではなく、社会総体の「戦時体制化」に押し流されているせいだろう。
とはいっても、今さら火野の作品を読み直そうとは思わない。これは火野にかぎらないけれど。
悠長に何かを再読している時間の余裕など、あまりわたしには残されているとは思えない日々……。


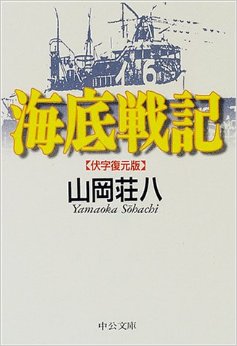
Share this content:
コメントを送信