更新日記2003.01.01
『文学史を読みかえる6 大転換期』ができた。
栗原幸夫氏によるわたしのインタビュー「60/70年代を語る 『煉獄回廊』を中心に」が載っている。巻頭の編者による覚書が、多岐にわたる論点を前奏的にまとめていて有益である。個々の論考がその挑発を充分に受け止めえていないのではないか(うーん)という不満は若干あるものの……。60年代と戦後文学(その決定的な変質・退潮と、最後の輝きへの助走期)なるテーマ――覚書で栗原が中野重治に託して示唆している――が欲しかった。てなこといって、自分で書けば良かったんであるが。
栗原が書いているようにギイ・ドゥボールの『スペクタクルの社会』は、きわめて60年代的な書物だったわけだ。翻訳のタイムラグのせいで、われわれがこれを読んだのは25年は後だったから、出遅れも甚だしいものだった。すでに歴史文書をひもとく冷たさで、白けながら目を通したのだ。文体の気取りとか独特のポーズはあっても、フランスのシチュアシオニストというのはアメリカのヒッピー・ムーヴメントの論客と、なんとよく似ていたことか。しかし考えてみたら、同じ時代の空気を吸っていたのだから、当たり前のことだ。そういえば、ドウボールもアビー・ホフマンも自殺してしまった。
あと本文では、小倉利丸が、P・K・ディックの60年代小説からドゥルーズ=ガタリ、アントニオ・ネグリ、ポストコロニアル批評への影響を指摘していた点に共感した。秋山洋子「対幻想のかげで 高橋たか子・矢川澄子・冥王まさ子の六十年代」も、けっこう刺激的であった(60年代の渋龍論は、サド裁判を軸に、文学vs国家権力論として展開してもらいたいけれど、それもまた一つの抑圧的な男流原理であろうか)。
と、まあ、なんだかんだいっても、読み応えは充分でした。
たしかに覚書のしめくくりにあるように、60年代において《私たちは、人類史の根源的な課題をかいま見た》といえるかもしれない。いや、そういわなければならないのかもしれない。むろんそのときわたしは二十歳だった。《ぼくは二十歳だった。それが人生で最良のときだとはだれにも言わせない》というポール・ニザンの言葉がひろまった、あの1968年、まさしく人が二十歳だったとはどういうことなのか。それは逃れることのできない問いとしてあったし、いまもある。もし、ある特有の時代に生まれることを単純に栄光と呼びたいのなら、他意のない単純明快さで、そっくり同じ時代に生を享けることを悲惨とも切って捨てられるのではないか。自分としては、60年代の再点検という作業が、自分の若いころの自慢話に収束していきかねないという恥ずかしさから抜け出ることが難しい。そのあたりのことは、インタビュー記事にも表われているような気がする。はたしてどう読まれるであろうか。
『文学史を読みかえる6 大転換期 60年代の光芒』
インパクト出版会
A5判 352ページ 2800円 ISBN4-7554-0128-3
2003年1月10日
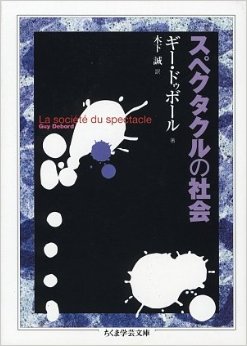
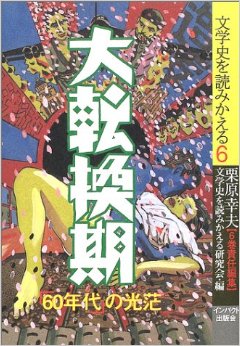
Share this content:
コメントを送信