更新日記2002.11.08
しばらく、煉獄回廊ディレクターズカットのページを埋めていくことにする。
連続していくのは曲馬館(小説では天馬団)に関連したエピソード。
精神病院の患者たちによる創作芝居に天馬団のメンバーがのりこんできて、記念写真を撮るみたいな芝居をするなと恫喝するシーンから。本では33から34に切りかわる中間になる。かなりまとめてカットして継ぎ合わせた。それを初稿の状態を復元してみる。
やはり冗長で説明に流れているので割愛して正解だったが、これはこれで作者としては捨てるにしのびない未定稿だという気はする。この流れのなかでいわゆる「不敬シーン」も出てくるが、これだけが問題になるとすれば本意ではない。あとの挿話ともども、何か「捨て子」にたいするかのような錯綜した感情が湧く。
いずれにしてもこのあたりの周辺が(実人生のうえでも)エピソード過剰であり、フィクションに吐露しようと試みても、あまりうまくいかない。「自伝」としても空転してしまうし、つくりすぎても意味がない。のみならず、つくらなければ読まれるほどの価値もない過去の遺物だ。
皇族の一員に扮装することが「歴史」をポートレートの額縁におさめてしまうような芝居に結果する。作り手の誠意を裏切ってしまうようにも。――そういう気の毒な失敗は、芝居の現場でけっこう目にしてきた。たとえば1977年の10月から11月にかけて、京大西部講堂で打ち上げられた芝居&映画&音楽の複合イベントのときのこと。三里塚全作品上映から故阿部薫のソロ、曲馬館の芝居など合計八プログラムの総合プロデュースといった役どころにわたしはいた。
そのなかの芝居のひとつが上に書いたような額縁芝居の終わり方をしてしまった。当時の現場としては、ただちに客席から「なんちゅう芝居をやりさらしとるんじゃ」という声があがることになる。ここから「セイブでつまらん芝居するやからはぶっつぶしたる」という直接行動まで、あと一歩だ。この抗議は間接にであれ、プロデュースしたわたしへの非難でもあり、「ぶっつぶされる」ときは区別なくひとからげにされる。結果的に騒動はおさめたけれど、自分が黒衣のような役にまわることに嫌気がさしてしまったことは否定できない。
このときのエピソードは下書きくらいはつくったのだけれど、どうにもストーリーの流れにはめこむことができなくて、あきらめてしまった。情景だけが浮き上がってしまうのだ。打ちこみのデータとしても残っていないだろう。データでかろうじて残った未定稿をこうして再生していると、またその前の段階で断念したエピソードが、二十数年たっていま初めて思い出すものも含めて、まざまざとよみがえってくる。それらの多くはすでに、語られる価値もないゴミなのかもしれない。輝く石だとはとてもいえない。
けれども。そうでないとしたら、それらはわたしという不当にとらえがたい断片をいくらか解明するに役立つのだろうか。いつの日にか、遠くない未来にでも。
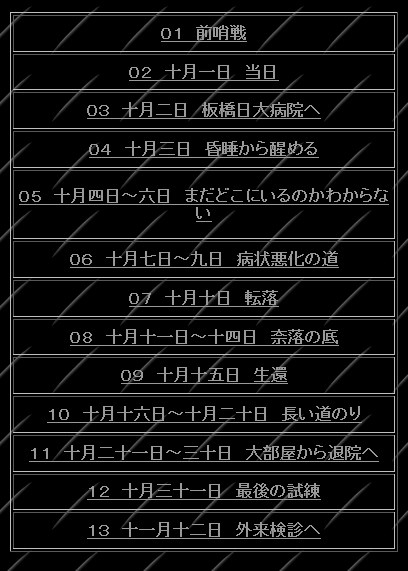
Share this content:
コメントを送信