その前夜 5
その前夜 五
ブラウニング、ドノソ
『モンスター・ショー 怪奇映画の文化史』を読んで以来、読みそこねたトッド・ブラウニングの伝記『フリークスを撮った男』を読む必要を感じている。ブラウニングは元サーカス芸人という経歴をかわれて「史上最凶のモンスター映画」と称された『フリークス』をつくった。ここでいう「モンスター」とは、MGMがこの映画のために世界じゅうからかり集めた「じっさいのフリークス」を指す。特殊メイクで映像のモンスターをつくりだすことの限界につきあたったハリウッドは、生身の「フリークス」たちをサーカス興業界などからかり集め、アル中で評判のブラウニング監督に映画をまかせた。
作られて(というより完成作を倉庫に葬られて)約半世紀後、わたしはこの作品を観る機会に恵まれた。まず驚いたのは、スクリーンに登場する「フリークス」たちに向けた作者のまなざしの公平さだ。月並みな言い方をするなら、ブラウニングは身体欠損者をごく平静に自然と見つめている。そこに差別感とか侮蔑の念は入っていない。『フリークス』より先に、デヴィッド・リンチの『エレファント・マン』を観たが、作者の畸形にたいする定見のなさ、興味本位に身体障害者を眺めたがる悪趣味に、つくづくうんざりしてしまった。畸形を見世物的観点からさらして見せるだけなので、不愉快になるのだ。比べてブラウニングは、どんな畸形に封印されているにせよ人間なのである、という信念を崩さない。
要するに、その公平なまなざしこそ『フリークス』という作品の抜きん出た普遍・不朽性だろう。
ところがじっさいには、映画『フリークス』の出演者のほとんどがブラウニングにたいして好い感情を残していないという。作品は時空を超えたが、撮影現場には怨嗟の声が積み重なったのだろう。ウェルナー・ヘルツォークの『小人の饗宴』を思い出した。「フリークス実写映画」としては『フリークス』以来であったかもしれないけれど、残念ながら、その印象はもはや淡く薄れている。ヘルツォークに関する現場エピソードも、およそネガティヴなものばかりだが、その点で、ブラウニングも似ていたのかもしれない。
ブラウニングとフォークナーの交響に心を引かれていたことがある。イメージを交差させたのは、ホセ・ドノソの『夜のみだらな鳥』だ。ハリウッド映画の撮影現場においては、ブラウニングとフォークナーの交渉はあった。どちらも映画界の不適応者であったことは、あらためていうまでもない。そのあたりは、『獣たちに故郷はいらない』のあとがきに書いた記憶がある。
『夜のみだらな鳥』は、読んだかぎりのラテンアメリカ小説のなかでは最高に衝撃的な作品だった。ドノソを読み返さないといけない。
十年前に『北米探偵小説論』の初版を出したときの反応の一つに、続編の『南米探偵小説論』を待望する、というのがあった。どなたに言われたのか、とんと憶えていない。一場のジョークみたいに受け取ったからだろう。ラテンアメリカ小説には、ご多分にもれず、入れこんだ時期があるが、点数的にそれほど読み切っていない。全体像をつかむとかにはほど遠い。原語のスペイン語テキストにもまったくなじみがない。ボルヘス&ビオイ=カサーレスの『ドン・イシドロ・パロディ 六つの難事件』を読むのにはどうすればいいのか途方に暮れていたこともある。
べつに今になってそのテーマが浮上してきたということではない。少なくとも『南米探偵小説論』などというのは、タイトルとしてはなかなかだとは思うが、それ以上の牽引力はないだろう。しかしいま身近に必要なのは、何にもまして何冊か未読のラテンアメリカ小説なのだという気がする。そこを抜ければ何かが見えてくるのではないか。いや、そこを抜けられなければ何も見えてこないのではないか……。
どうも書いていることが混乱してきた。脳が微熱をもってゆらゆらとたゆたっている。秋虫たちの音色がかまびすしい。短く済ます文章なのに、中途半端なまま、次の展開を見つけられない。明日だ。
明日になればもう少しマシなことを考えつくだろう……。
2001.9.2
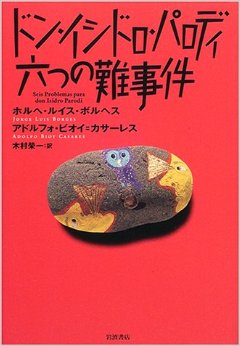

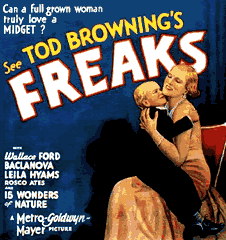


Share this content:
コメントを送信