その前夜 1
引き出しのなかを整理していたら、比較的新しい反故が出てきた。二〇〇一年の八月末に集中して書いた文章だ。
ホームページの連載用に下書きしていたものと思われる。時期的には、「9.11」の前夜になるけれど、個人的にいって脳炎で倒れる前夜だから、こちらの意味合いのほうが強い。書いたことすらきれいに忘れてしまっていたので、対面すると不思議な感に打たれる。退院の後、いろいろなことが取り散らかって、抜け落ちていった。そのいくつかの項目の一つだ。何やら遺書めいた一節すらあって、不気味だと感じるのは本人だけかもしれない。
いくらか求心力に欠けるものもあるが、まあ許せる範囲だろう。少し整理してデータ化しておく。六本あったが、一本は他に書いた内容と重複していたから割愛する。
その前夜。
五回ヴァージョンだ。
元に考えていたタイトルは「銀河コオロギ通信」という。用意していた前書きは以下――。
今いつも通っている道は秋虫たちのオーケストラに包まれて、むせかえるばかりの賑やかさだ。耳を澄ますまでもなく、全身にさんさんと降りそそいでくる。現在形の心境を何に託すかは難しい選択だ。とりあえずはこの音色に乗せて、二〇〇一年の銀河を書いていこう。
その前夜 一
あるポストコロニアル小説
ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』をめぐって
覇気を喪った中年イギリス人と二十歳前のジャマイカ人娘の出会い。いささか毛色の変わった父と母のなれそめから始まるこの小説はやはり、ロレンス・スターンの『トリストラム・シャンディ』風の語りにつらなる自伝文学に属するのだろう。しかしこの自伝は作者にあっては、たんに系譜をたどりアイデンティティを測定するのみではありえない。もちろんその側面も含むが、たんにそれだけに終わらないのだ。なぜなら彼女の出生で民族の血が混じり合ったように、系譜は二つの民族に分かれていくからだ。
運命について作者は楽観をもって相対している。二十世紀は「旅人の世紀だ」と彼女は言い切る。民族が、革命や戦争につづいて、二十世紀の後半を特徴づけるキー概念だったことを知る者には、それはいささか軽すぎる断定にきこえる。そして作者の年齢を考えてみれば、その軽さも、歴史を知らない不遜さなのかと納得できる。しかしそうした納得は、『ホワイト・ティース』という作品全体の豊饒さによって、あっさりと退けられるに違いない。
移民・難民・亡命。二十世紀の民族移動――どの世紀においても変わりはないかもしれないが――は膨大な悲劇をともなった。悲劇の末裔たちに求められるのは、いうならば、その重さにたいする忠誠だ。歴史を知らない者は己れを知ることができないというドグマは、あたかも信仰のように、より若い世代に伝達されようとする。輪が途切れるかもしれない予感に伝達者は苛立つ。しかしただ従順に大人の教えを学ぶ者が賢い若者というわけではない。
『ホワイト・ティース』はいっけん公平にみえて、じつは父祖にたいしてこの上なく残酷であるかもしれない視点に貫かれている。存在そのものの日常的雑駁さを呈示するほかなかった結果か、作者は、歴史について達観とも思える境地を身につけている。作者の生理的年齢によって作品を規定するのは短絡的すぎるとはいえ、これは、一般的には若さとは両立しえない観点だ。もしくは、革命と戦争と民族の世紀がいったん区切られてしまった「後に・来た」年代に特有の醒めはてた歴史意識とみなすべきだろうか。
作品にとって作者の出自は無視できない要素であるという意味で、この作品は、ポストコロニアル文学の収穫という評価を排することはできない。ポストコロニアルの子弟によって書かれた新時代のマイノリティ文学。その日常は、混民族混合であり、一つの民族を明確に被害者とみなす図式は、すでに成り立ちようがない。
『ホワイト・ティース』を自伝文学として扱うにしろ、北米黒人男性小説(たとえば、リチャード・ライトの『ラウド・トゥディ』やジェイムズ・ボールドウィンの『山にのぼりて告げよ』など)には明瞭にあった、そしてそれがあたかも運命の軛のごとく捉えられていた、(抑圧された)単一民族コミュニティという舞台はまったく過去のものなった。――それを認めなければ話は始まらないようだ。
「過去のもの」とは危険な言い方であるが、およそ半世紀さかのぼるアフリカ系アメリカ人のそれぞれ長編第一作を比較に例示してみたのは、主として主人公の位置を測定してみたいからだ。両者があまりにも隔絶した世界として印象されるとすれば、もう少し時代を接近させて別の例をあげてもよい。およそ十年前の北米黒人女性小説――テリー・マクミランの処女作『ため息つかせて』などは最適の比較対象かもしれない。この作品は、ホイットニー・ヒューストンら有名スターの主演によって映画化されたことからもわかるように、中流黒人女性の「等身大な」生活と意見を率直に押し出したもので、ほぼポストモダニズム小説の流れにあったものといえる。
作者が乗り越えようと視野に入れていたのは、直接にはブラック・フェミニズムであり、間接にはブラック・フェミニズムの非難にさらされたブラック・マッチスモである。マクミランは先行するコロニアル文学の影響圏から脱け出そうと懸命になり、その結果、ノイジーで脱民族性の明らかな、軽い文体を「九〇年代」スタイルとして定着させようと試みた。
歴史を受け継ごうとする者はその重圧から逃れられないと思わせる。それは、批判的なモチーフをいだけばいだくほど、いっそう重くのしかかってくるようだ。『ホワイト・ティース』の呈示する猥雑な日常の豊饒さは、逆にいって、作者のなかの「コロニアルの女」がその日常によってどれだけ日々傷つけられたかのシグナルでもある。ただ作者は、自分がもはや「コロニアルの女」としては語れないことを自覚していた。また父祖からのお仕着せの言葉をそのまま流用することは正しくはあるまい。それはかえって自らの系譜を愚弄することにすらつながるのではないか。
ポストコロニアル小説の規範が、たとえばカリブ人女性作家ジャマイカ・キンケイドにあるとしても、後続する書き手はそれを手本にはできないのである。
ではどうすればいいのか。
そこで選ばれたのが、二百年前のロレンス・スターンの文体だった。
二十世紀は「旅人の世紀」と断定するのと同じように、「人間存在は歯だ」と、作者はここで提起している。歯が人間存在の基底だ。どんな有色人種であろうと歯は白い。肌の色で区別されるもろもろも、白い歯という普遍的共通性によって意味をなくす。――これがタイトルにこめられた希望であるだろう。
『ホワイト・ティース』は父祖たちの歴史=物語〈イストワール〉に関心を持たないわけではない。むしろルーツを探ることによって小説世界はいっそう闊達にくりひろげられていく。だがそのルーツは、たんなるルーツというより、歯のルーツだったりする。
他に見逃せないことは、歴史の垂直軸とともに世界同時性(グローバリゼーション文化)の水平軸がある。ここでは、やはりアメリカン・サブカルチャーの遍在性という問題につきあたってくる。最も目につくのは、パブリック・エナミーに代表されるブラック・コンテンポラリーとハリウッド製ギャング映画だ。或る急進派ムスリム青年の内面は、次のように定着される――。
《頭のなかに『グッドフェローズ』のオープニングが流れ、潜在意識だとミラトが思っている部分にこの言葉がうねるのだ。思い出せるかぎり昔から、おれはいつだってギャングになりたいと思ってた。》 ギャングの一語がムスリムに置き替わる。これじゃいけない。《なんとかしようとする。だが、ミラトの頭はうまく働かないので、たいていは、結局、頭を反らして肩をつきだしたリオッタ・スタイルでドアを押し開けることになってしまう。(中略)
ミラトはグリーンのボウタイをまっすぐにし、リオッタのように(威嚇と魅力たっぷりに)音をたてずに前へ進み、台所のドアを開け(「思い出せるかぎり昔から……」)、二組の目が、スコセッシのキャメラのように自分の顔を向き、焦点をあわせるのを待った。》
――アメリカ白人文化が野放図に発信する「人間性の普遍」イメージとその影響。もちろんこれはオリジナルなシーンでも、事新しい発見でもない。「コロニアル文学」が、たとえばトニ・モリスンの『青い眼がほしい』のように、一貫して追求しつづけてきた「倒錯した白人願望」テーマのヴァリエーションの一つなのである。
さてジャマイカ系イギリス人女性作家の才気換発たる処女小説がわれわれにとって持つ意味は何なのだろう。彼女が駆使するポストモダニズム小説のさまざまな技法に学ぶべきところは多々あるだろう。しかし作者が描ききってみせる混民族社会の混乱に関しては、それをどれだけ認識できるかの問題が残る。あまりに彼我の状況は離れているようにも思える。
ポストコロニアル文学という一語をとっても、そうだ。世界史における一般的な意味でのポストコロニアル歴史過程を体験してこなかった日本人は、どうすればポストコロニアル文学を全的に理解できるのか。――という素朴な疑問から自由になれない。あるいは、世界史にはヘーゲル的な理性なんか存在しないし、そもそも一般性なんてものは幻想にすぎない、と開き直ってみせれば済むのだろうか。近代アジアで唯一の植民地保有宗主国であった日本は、敗戦によってその植民地を不当に奪われた結果、イギリスやフランスといった「一流の帝国主義国家」がくぐった流血の脱植民地化過程を免れ、手を汚すこともなかった。朝鮮済州島のパルチザン闘争や台湾の独立運動にたいして、直接に敵対したのは占領国アメリカだった。その結果、日本におけるポストコロニアル意識とは、ほぼ学術的興味の範疇にとどまりつづけた。耳慣れない外来語による、外国思想と外国小説とが気まぐれに消費されるばかりだったのだ。
さて『ホワイト・ティース』のように複雑に組成された作品から、後発的に学ぶことは可能なのだろうか。
2001.8.21
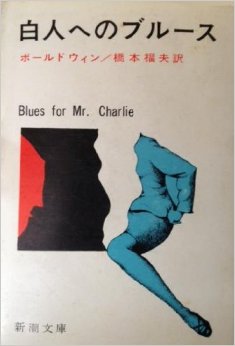
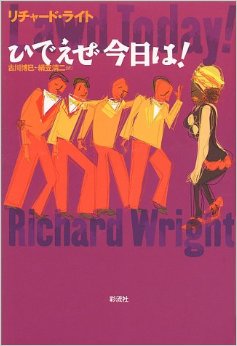
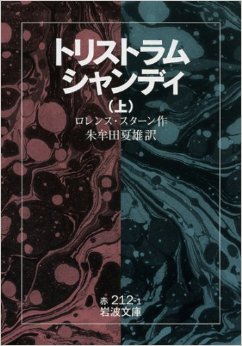
Share this content:

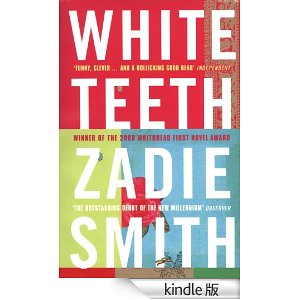
コメントを送信