その前夜 4
その前夜 四
ある在日作家の肖像
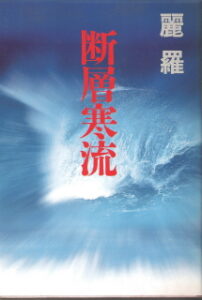
少し前のことになるが、麗羅が亡くなった。在日朝鮮人文学者としては珍しく、ミステリ系の作品を生産しつづけた人だ。一度お会いしたことがあるが、うわべは友好的な会話ながら、政治的な立場の相違もあってか、「この若造めが」という本心がそれとなく伝わってきて、わたしには居心地が悪かったことを憶えている。
大東亜戦争軍属と朝鮮戦争義勇軍と。その両方に従軍体験を持っていたのは、この人だけだろう。『体験的朝鮮戦争』は、そのあたりのことをぼやかして記述しているような気もしたが、あんがいあれが正直なぎりぎりの「告白」かもしれないと、今は思う。
わたしがこの作家に注目したのは、『桜子は帰ってきたか』がきっかけだった。『詩と思想』という雑誌があって、そこにタダ原稿のミステリ時評を隔月連載させてもらっていたころ。1983年だ。そのあと主な作品を対象に「黄色植民地人の憤怒」を書いて、二冊目の本『獣たちに故郷はいらない』の一章にあてた。その章はまた、いくらか書き直して『北米探偵小説論』の増補版に組み入れている。その後の何冊かについては、『サンデー毎日』の書評で取り上げ、後に『これがミステリガイドだ! 1988-2000』に収録した。正直なところ、かなりのヒイキ評で持ち上げたのだった。
わたしの論考の後、麗羅については川村湊が書いている。他に主だった注目はなかったと思う。
実生活の側面ではずいぶん無頼のエピソードを残しているとも聞いたことがあるが、そうしたアンダーグラウンドの臭いが作品に充満することはなかった。ある時期までの在日朝鮮人文学は、アイデンティティ探究の知識人小説という側面が色濃かった。麗羅は、その意味では、まったく孤立した位置に立っていたといえるだろう。
在日のノワールな領域は、後に、梁石日によってダイナミックに掘り下げられることになる。梁石日の全面開花を見届けてしまった観点からすれば、麗羅の位置はひどく曖昧で過渡的で、それだけ商業ベースの要請に左右されていたように思える。
在日文学にも、当然ながら、文学的営為と大衆迎合的な試行との分裂がみられる。在日朝鮮人文学史にあって、だれがいっとう初めに俗悪な大衆小説を書いたのかと問えば答えは自明であるだろう。張赫宙――野口赫宙がその名だ。ただわたしは、一部の日本人の研究者が(自分に朝鮮民族の血が流れているようなつもりでか)張を非難することに多大な違和感をいだく。端的にいって、日本人には、文学的にせよ道徳的にせよ、張を断罪する資格などないではないか――。非常に素朴な出発点とはいえ、そこに目を向けない「文学論」などは無益に終わる(この点は、踏みこむと問題が広範に過ぎるので、ここではこれ以上は展開できない)。
一つだけいっておけば、張の戦後の野口名による日本語作品をリスト・アップしていく作業は猛烈な憂愁をともなう。散在している作品の目録をつくり、そしてその一点一点を探し出して綿密に読み取っていく――これがそもそもの文学研究の第一歩だ。すでに何人もの研究者の研鑚を通して全集が発刊されている文学者であれば別だが、野口の場合は、一次的なリサーチから始めなければならない。一方で正直なところ、それほどの価値はないだろうという予断も強い。だが、張赫宙は、その文学的価値においてではなく、むしろ逆に、非文学的位置において、正確な測定をなされねばならない存在なのだといえよう。それは成すべき作業であるにもかかわらず、だれも果たしてはいないのだ。
梁石日の『断層海流』が出て、話題を呼んだしばらく後のことだったか。麗羅の『断層寒流』が出た。タイトルの類似に少し戸惑った。ストーリー的には、遺憾ながら、まとまりに欠けるところが多かった。『断層海流』の話を作者と交わしていた時。その構成のあまりの奔放闊達さについて口をすべらせて、梁さんの怒りをかった話の流れで、麗羅の新作も話題にあがったことがある。
「なんやね、あれは」「まあ、ちょっと困りますね」「きみ、読んだんけ」「がっかりしましたね」
小説としては、それが麗羅の最後の本になったはずだ。
2001.8.31
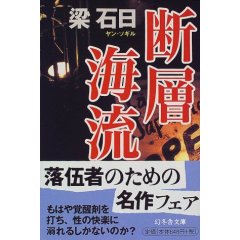
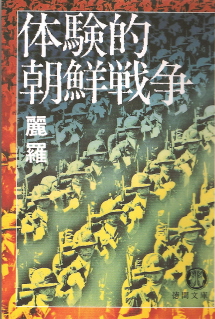
Share this content:
コメントを送信