アンプラグド&アンプラグド&アンプラグド&…
終日、ニール・ヤングの『アンプラグド』を聴いている。
わたしの身辺にはこの他およそ何もない。
しかし、八曲目にくると、心おだやかでなくなるわけでもない。
『ヘルプレス』
この曲は、結局、これでスリー・ヴァージョンを聴くことになる。べつにコレクターをやっているのではない。偶然の所産だ。
一は『いちご白書』のサウンド・トラック盤で、CSN&Y時代のヴァージョンだ。
二は、ザ・バンドの解散コンサート・フィルム『ラスト・ワルツ』のサウンド・トラック盤。
三が、最近の『アンプラグド』のもの。
一が一九七一年、二が七八年、三が九三年と、およそ十年ごとの節目と考えてよいか。といっても各ヴァージョンにそれほど著しい違いはない。ほとんど同じだといってもいいくらいだ。好みでいうなら二になるだろう。これはほぼ完璧に酩酊した状態で、ニール・ヤングがこれを唄っているフィルムを観ているせいかもしれない。その印象が決定的なのだ。おかげでこの歌い手といえば、『孤独の旅路(ハート・オブ・ゴールド)』と『ヘルプレス』の他、さっぱり耳に残っていない結果となった。それも遠い昔のことだ。
マーティン・スコセッシが監督したドキュメンタリー『ラスト・ワルツ』を、わたしは”退役兵士の詩”にすぎないと否定的にながめていた。だがもっと胸の悪くなるようなコンサート・フィルムは他に沢山観ているから、言葉とは裏腹な好感はもっていたかもしれない。レコード、テープ共に聴き古したと憶えている。一番好きなのは、エミルー・ハリスがリック・ダンゴと『エヴァンジュリン』を唄う、スタジオ撮影の場面だった。『アイ・シャル・ビー・リリースト』は幸いなことに(?)このフィルムでは、ディランのソロになっている。最後の大合唱にはとられていない。
何か七〇年代後半のコンサートというとこの歌なしには終わらなかったような固着した記憶がある。手に手をとりあって、小異を捨て大コーラスに融合する。そういう悪夢のようなイメージが一時期、『アイ・シャル・ビー・リリースト』にはついてまわっていた。
そう考えてみるとニール・ヤングには変わり目がない。起伏もなく、中心点に立つようなこともなかった。いつも変わらずに、請われては『ヘルプレス』を唄う男。これはかえって稀有なことなのかもしれない。とくにいえば、七一年のヴァージョンは、声の質がかなり硬質に澄んでいたような気がする、といった程度の違いはある。全く同じ歌を、同じふうに唄っているのだ。二十年間、外の世界では、何事もなかったかのように。そう錯覚させるような安心感がここにはある。
『いちご白書』では挿入曲だったから、どの場面のバックにこの曲が使われていたのか、全く憶えていない。もう一度映画を観て確かめようという気にはとてもなれない。『いちご白書』はニューシネマの時代の、いわゆる一つの典型的な「学園闘争青春ドラマ」だったから、リヴァイバルされてくる可能性はあるだろうけれど。この映画でむしろ印象深かったのは、バフィ・セント・メリーの『サークル・ゲーム』がタイトル・バックに使われていたことだった。どこまでもセンチメンタリズムに引きまわされている。そこにとらわれてしかこの映画の想い出というものはない。古びた幻想の甘ったるい怠惰からいまさらこのものを引き出してくる気はさらさらない。
ほとんど空で覚えてしまった『ヘルプレス』の唄い出しの数行――。
“There is a town in north Ontario
With dream comfort memory despair
And in my mind I still need a place to go
All my changes were there”
たぶんこういうものが不断に巻き戻されてくる感情の回路というものがあり、こういうものがスリー・ヴァージョンもあるかのように十年の節目をもってリピートされまた消えてゆき、再びアンプラグドな心もように巻き戻されてくる……といったことが問題なのだ。『サークル・ゲーム』の一節でいえば、《&・シーズン・ゴー・ラウンド&ラウンド&ラウンド&…》 レコードならば針がとび、いつまでたっても次のフレーズが出てこない。
人間の思想というものは、それが極限に考え抜かれた瞬間よりも、ある個人の中で深まるものではない。想像力の飛翔についても同じことがいえるだろう。だから後退して出ていった者たちにそれほど興味を持続させることはできない。かれらは最も輝いていた頂点において記憶されれば良いだろう。『ビフォー・ザ・フラッド』のザ・バンドのように。色褪せた歳月をそこに重ねてみても空しいだけだ。
で、ニール・ヤングがどこにいるのか、正直いってわたしにはわからない。見当がつかない。『ラスト・ワルツ』で洞窟のような空ろな眼をして『ヘルプレス』を唄っていたそのままの姿で、同じ椅子に十数年、腰掛け続け、全く変節することもなく退役もせず復員もせず、左肩を落としたまるきり同じ座り方、アコースティック・ギター、ハーモニカ、濁ることのない声質、時代が自分をすりぬけていくとでもいうように、『アンプラグド』の世界にもぐりこむことができたのかもしれない。
『ラスト・ワルツ』のニール・ヤングには何かさらし物にされているような悲惨なイメージがはりついていた。あの映画の最も暗い部分に身を置いていたのだ。たんにオーヴァー・トリップの状態で演奏していたのではない。今にもほとんど意識をなくしそうになった自分を支えている……いや、全く意識が召還されてしまった無の状態で肉体の抜け殻だけが歌を唄っているような。崩れ落ちる寸前の残骸が余力のすべてを使いきって己の外形をとりつくろっているような。
七〇年代末にはそういう固有の感情の捨て場所を捜しあぐねていた。そうした痛ましい体験のスクラップを身近にみすぎていたからかもしれない。そういうものに限度はないのだった。歴史のクズ箱に取り残され、ただ退役する以外に手段を失った者らの……。
ところで『アンプラグド』のニール・ヤングからは、そうした悲惨なイメージが払拭されている。生き延びたものの静謐と安息がかれを守っているのかもしれない。
歴史の経験というものは無慈悲なトゲももった牢獄だ。いったんそこに捕らわれた人間を放すことはない。退役は少なくとも意思的な選択のように思えて、全く異なった奈落への転落だった。逃避の途はいくらでもあるし、完璧にないともいえる。
再びの「全共闘ブーム」の予兆がある。下らない・表層の・言説だけの・カタログ的な・一過性のものだが。相変わらず歴史に関わった個人の生がさらし物にされる。死刑確定犯の手になる奇異なイラストがさらし物にされる。(彼女は充分に償ったではないか)。何をもってしても裁き得るとするのは言論の迷蒙にすぎない。十年前のブームより深まるものがあるとすれば、この迷蒙と年少世代からの行きはぐれたルサンチマンばかりだろう。歴史の経験はいっそうの理解の通路をもつより、たやすく錯乱に道をあけわたすだろう。後続世代の声は一層の混乱した石となってわたしらを襲うはずだ。経験は知識として伝達されると同時に、色褪せた遺物さながら、侮蔑この上ない対象となる。経験をうまずたゆまず正確に語り伝えるという選択は、この両義性に阻まれて立往生する。
このとき、言葉を救うものは徹底的に言葉ではありえない。そうしたおそるべき時代なのだ。――だがわたしは言葉を信じる。
京都大学を知る本 93.8

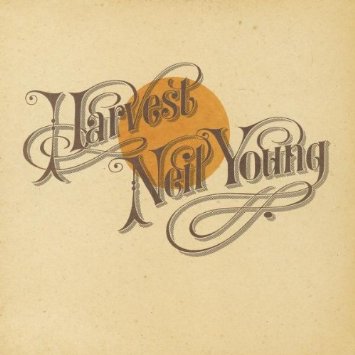
Share this content:
コメントを送信